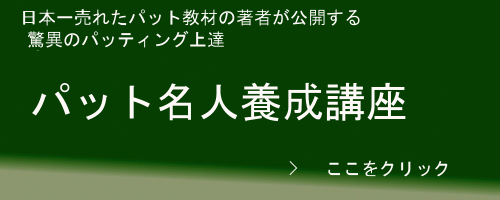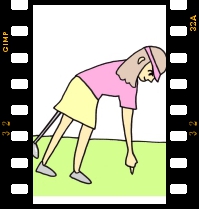 太めのパターグリップが人気を集めています。こうした極太グリップが流行するのは、ある意味では必然という見方をする人も多く見られます。
太めのパターグリップが人気を集めています。こうした極太グリップが流行するのは、ある意味では必然という見方をする人も多く見られます。
ゴルフクラブに関する有名な言葉はいくつかありますがの中には「グリップはだけが、ゴルファーがクラブと接する部分」という言葉があります。
しかし、これまではことパターに関しては、そうした感覚が薄かったようにも思えます。
しかし、近年になってアメリカツアーで、フィル・ミケルソンやセルジオ・ガルシアが「スーパーストローク」という極太グリップを使用するようになりました。
それ以降は、パターのグリップの太さに多くの人が注目するようになってきたことは確かでしょう。
このスーパーストロークの特徴は、太くて手首の動きを抑制する効果があることが一番に挙げられます。
さらに右手と左手がくる位置のグリップの太さが同じに設計されているので、右手の動きをより強く抑えてくれる点に工夫があることを忘れるわけにはいきません。
今のゴルフクラブのグリップは細すぎるのではないかと思っていたゴルファーは日本でも少なくなかったようです。
欧米人と比べれば、手の小さい東洋人には細いグリップが合っているという考え方がることも事実です。
しかし、テニスの世界で錦織圭が持つテニスラケットも、イチローが振る野球のバットも、ゴルフクラブのグリップと比較すれば太いのです。
そう考えれば、日本人だからといって細いグリップのほうがいいと単純に決めつけるのは間違いかもしれません。
むしろ太いグリップにしたほうがメリットが大きいように感じている人も確かに存在するのです。
グリップを太くするメリットとしては、ギュッと力をこめて握らなくなることや指ではなく手のひらで握ろうとするというメリットなどが挙げられます。
フェースの向きを安定
クラブフェースの向きの安定性に関しての名言として思い出してほしい言葉に、「大きな筋肉でスイングする」というものがあります。
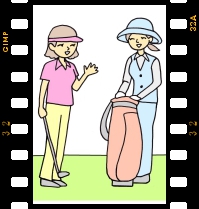 これはフルショットに限った話ではなく、パッティングのような小さな動きで小さなエネルギーしか必要としないスイングにも当てはまることと言えます。
これはフルショットに限った話ではなく、パッティングのような小さな動きで小さなエネルギーしか必要としないスイングにも当てはまることと言えます。
手先ばかりを使えば、リズムは細かく乱れやすくなりますし、インパクトでのクラブフェースの向きから安定性を欠くことになるケースが非常に多いのです。
プロゴルファーは厚手のグローブをはめてパッティングの練習をすることがよくありますが、これも手先の器用さを使わないで鈍感な状態にして使うイメージを考えているのではないかと思われます。
プロゴルファーのように練習量を多く確保できるような状況であれば、器用な手先を積極的に使うストロークの仕方を追求する道もあるはずなのです。
しかし、現在のような高速グリーンが当たり前になった世界のツアーを観戦していても、そのようなパッティングスタイルで成功しているプロを見つけることは不可能でしょう。
この事実はプロゴルファーと言えども、その大半が「手先を使いたくない」と考えている証拠のように思えます。
スポンサード リンク
現在PGAツアーの中、スーパーストロークという太いグリップが流行っている理由としても、そうした意図があるためだと考えられます。
太いグリップを握ることで、手首や指を使う余地を残さないようにする結果として、リズムが安定させやすくなる上に、グリッププレッシャーをコンスタントに保ったストロークが可能になります。
フェース面の向きから不安的な要素を排除し、なおかつ、リストの角度も維持できて、適切なヘッドスピードやロフト角でも打てるようになるおかげで距離感もよくなっていくことも容易に予想がつきます。
大きな筋肉とは、指先や手先以外のすべての筋肉だと考えてもあながち間違いとは言えないでしょう。
手先を使わないパッティングの場合、その他の部分を必要なだけ動かすことをしないと、ストロークがうまく作れなくなるのです。
指先や手先以外となると腕、肩、背中、お腹、胸などをはじめとして、下半身も含まれます。
結果さえついてくるのであればイメージのしやすい部位を意識して、狙ったラインに、思いどおりのスピードで打ち出せるように考える方法を積極的に採用すべきではないでしょうか。
下半身に関しては、必ずしも止める意識を持つ必要はないかもしれませんが、結果的には動かないほうが、トータル的にストロークを見た場合や、フェースの向きも安定性を考えた場合に有利なのは確かでしょう。
更に言えば、ロングパットともなると、多少なりとも下半身を動かしたほうが、手先の力を使わなくても良いという状態を作るべきかもしれません。
遠くまで転がすことを考慮すれば、自ずと生まれてくる動きを信じてに任せるという考え方でも構わないでしょう。
他のショットでも下半身を動かしながら、クラブフェースの向きをターゲット方向に合わせているわけですから、パッティングについても下半身が動くから方向性の点で良くないという結論に至ることはないでしょう。